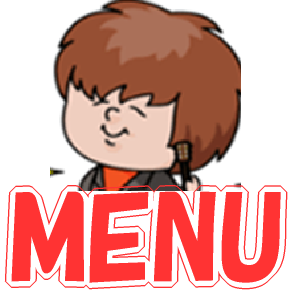【お正月のラブストーリー】
2005年の大晦日のにぎわいは、
去年となにも変わらない。
ただ一つだけ、違うのは、クリスマスまでつき合っていた敬子が、そこにいないという事だ。
マサルは一人、流行の流れが速くなった、お笑いタレントが沢山出てくるテレビをボーッと眺めていた。
仕事おさめも、おとといで、終わっていて、なんの予定もない一人の部屋には、
無造作にコンビニのビニール袋が散らばっている。
「ビールでも飲むか」
そう、一人ごとをつぶやいて、冷蔵庫をあけた。
「あれ?もうなかったんだ」
両ヒザを付いて、のぞき込んだ
冷蔵庫の中にあるのもは、賞味期限の切れたマヨネーズと、もうすぐでカラになる
ペットボトルのウーロン茶だけだった。
「しょうがない、買ってくるか?」
マサルはあきらめて、冷蔵庫の扉を閉めようとした、
その時、
「カラン」と、
なにやら、ガラスのような音に気付いた。
「なんだろう?」
もう一度冷蔵庫を開けて、奥の方をのぞき込むと、黒いビンを見つけた。
「これも、もう賞味期限、切れてるなー」
マサルはそのビンを左手でつかむと、
はがれかけたラベルをクルっと回して見つめた。
それは、昨年の大晦日に、敬子と一緒に食べた、年越しそばのツユのビンだった。
「懐かしいなー」
マサルの瞳は遠くを見つめていた。
2004年の大晦日。外は大雪がふったせいで、部屋の中もだいぶ冷えていた。
「コタツ強くなってる?」
マサルが肩を小さくしながら言った。
「なってるよー」
コタツの布団を持ち上げながら敬子が言った。テレビから流れる歌声を聞きながら、
二人はさっき打ったばかりの、年越しソバを食べていた。
いくら寒い冬と言っても、二人で過ごす時間は、その寒ささえ気付かないほど、幸せな時間だった。
「どっちが勝と思う?」
「なにが?」
「紅白」
「白に決まってるだろ」
「いや、赤だと思うな」
「どっちでもいいよ」。
マサルの最後のセリフは真実だった。
『どちらでもいい』
ただ二人で一緒にいられればそれでよかった。
「5,4,3,」 カウントダウンがはじまった。マサルはあと少し残ったビールを飲み干しながら、声を出してテレビと一緒にカウントダウンをする、敬子を見ていた。
もう25も過ぎたというのに、そんな無邪気な彼女のを、マサルは本気で愛していた。
「あけましておめでとうございまーす!」
テレビから流れてくる司会者の声や、中継のディズニーランドや渋谷の街が、新年をあざやかに演出していた。
「今年も、よろしくお願いします」
マサルはちょっと照れたように敬子に言った。
「こちらこそ」
普段使わない敬語が、やけに、もどかしくて、二人で笑った。
「フーおなかいっぱいだ」
ほんのり赤くなった顔でマサルが言った。
「ネェネェ、ヨーグルト食べたくない?」
その一言で二人はコンビニへと出かけて行った。
「丁度ビールも切らしてるから、買っていこう!」
3本の缶を景気よくカゴに入れた。
「ちょっと!飲み過ぎじゃないの?」
敬子の少し怒った声に、マサルはわざと小さくなって見せた。
お酒を飲んでしまったので、歩いて買い物に来た二人だったが、帰りの道も、手をつなげば、寒さなんて少しも感じなかった。
あれから、時が流れ、忙しくなった仕事と、会えなくなった時間が、焼けた夏の砂浜を秋の風が通り過ぎるように、二人の心をゆっくりと冷ましていった。
特に理由があった訳ではないが、ただなんとなく、二人は離れて行った。
「もう会わない方がいいよね」
敬子の最後の一言にマサルは何も言えずに、ただ小さく、うなずいただけだった。
クリスマスのネオンに輝いた駅のロータリーに、消えてゆく後ろ姿を、マサルはいつまでも見ていた。
こうして、2005年の大晦日を向かえた。
「さあ、今年も残すところあと5分となりました」
テレビの中は去ってゆく、2005年の想い出と、やってくる2006年の希望に満ちていた。
「もうすぐで終わりか」
マサルのため息には、終わってゆく、今年と、そして終わってゆく、愛が重なっていた。
「5,4,3,」
カウントダウンがはじまった。
そのカウントダウンがまるで、愛が終わってゆくカウントダウンに聞こえて、思わずテレビのスイッチを消した。
さっきとは打って変わって静かな一人の部屋が、ブラウン管に反射して映った。
「何してるかな?今頃」
いくつもの敬子との想い出が、頭の中によみがえってくる。
夏の海も、春のサクラも、秋の紅葉も、そして、今はもう、去年になってしまった、
冬の想い出。
マサルは一度だけ、目をこすった後、大きなため息を付いて、また一人ごとを言った。
「さて、ビールでも買いに行くか」。
今年は雪もふっていないのに、去年よりも寒く感じた。
「さむい、さむい」
上着のチャックを閉めて、歩いてコンビニへと向かった。
小さな曲がり角を曲がった、その瞬間、
マサルは、目をうたぐった。
「あけましておめでとう」
一晩中、泣きはらしたように、目を真っ赤にして、そう声をかけたのは、まぎれもない敬子の姿だった。
「どうしたの?」
マサルが聞くと、敬子は崩れるように、マサルの胸へと飛び込んだ。
「やっぱり好きだよ」
涙を流して、敬子は何度もそう言った。
マサルは敬子の体を、強く抱きしめた
「俺も好きだよ」
二人は、新年を向かえたばかりの街で、
しばらく抱き合っていた。
「今年も宜しくお願いします」
マサルが照れたように言った。
「こちらこそ」
敬子は、そう言って泣きながら、やっと笑った。
敬子は抱えてきた、包みを差し出してこう言った
「これ、ウチで作った手打ちソバなんだけど、年明けちゃったけど、一緒に食べよう」
マサルも笑顔になって、うなずいた。
「あっ、でもつゆがないよ」
さっき冷蔵庫で見たビンの事を思い出した。「いいよ!二人で買いに行こうよ!」
「そうだな!ビールも切れてたし!」
「またー、飲み過ぎないでよ!」
「わかってるって!正月くらい大目に見てよ」「もー!その変わり私にヨーグルト買ってよ!」
「はいはい!わかりました」
二人の笑い声は、2006年
はじまったばかりの、冬の空に、
1年前と同じように、
優しく、響いていた。